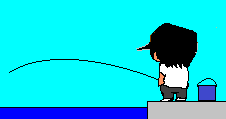床の上に100kgのバーベルが置いてあるとします。
それを、『どんな姿勢でも動作でも良いので、床から数センチ持ち上げてください』、
と言われたら、実際にできるかどうかは別として、やり方を想像できないということは無いでしょう。
いわゆる重量挙げの選手ではなくても、『力持ち』の人なら出来てしまうかもしれませんし、
できない場合でも、どうしたら出来るようになるのか想像することはできると思います。
また、100mを10秒台で走れと言われたら、
これも同じようなことで、少なくても『走る』という動作は誰でも出来ると思います。
これらは、『できる・できない』の違いが、どんな能力の違いなのか?、比較的わかりやすい『目に見える身体能力』だといえます。
それに対して、
ある茶道の先生が、完全に正座した状態から一挙動で(ノーモーションで)立ち上がったり、
ある舞踏家が、他の部位を微動だにせずに手首から先だけを動かしたり、
これらは、一見しただけでは、その能力の特殊さが理解しにくく、
多くの人は、実際にやってみて初めて、『真似できない』ということに気づきます。
さらに、なぜ出来ないのか? どうやったら出来るのかを想像できないと思います。
つまり、『できる・できない』の違いが、どんな能力の違いなのか?わかりにくい『目に見えない身体能力』です。
『目に見える身体能力』は、そのトレーニング方法も明解で、多くの人が同じように身につけられますが、
『目に見えない身体能力』は、『極意』という言葉に置き換えられ、その構造自体を明解に説明することが困難な場合が多いため、そのトレーニング方法も明解ではなく、多くの人が同じように身につけられません。(合気道などの『合気(あいき)』という概念がそれにあたると思います)
『目に見えない身体能力』=『極意』を修得するための道筋として、
一定の条件(制約)の元で要求される事を達成するという方法があります。
達成するためには『極意』の修得が不可欠であるため、『ごまかしがきかない』という意味では、確実に『極意』に行き着くというわけです。
その一定の条件(制約)が『型(形)』というものです。
逆に言えば、極意を持つ人の型と、そうでない人の型は、一目で分かります。
太極拳も極意を修得するための型です。